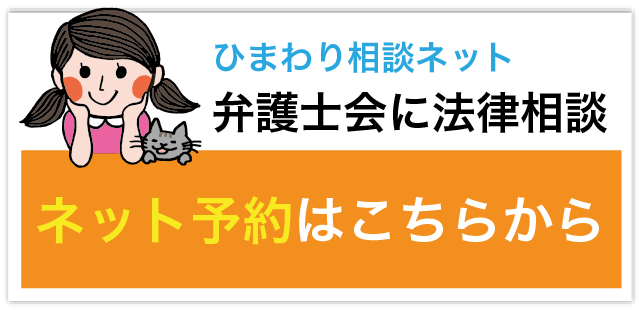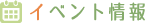政府は、2023年3月7日、通常国会において、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)改正案を提出し、同年4月13日、審議が開始された。この入管法改正案は、2021年に廃案となった入管法改正案の大枠を維持したままのものである。
しかし、2021年に上記法案が廃案となったのは、当会が、2020年10月2日付「『送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言』に基づく刑事罰導入等に対する声明」で指摘した、送還停止効の例外の導入や退去強制拒否罪の創設等、複数の重大な問題をはらんでおり、それらについて一般市民を含めた広範な国民から反対の声が強く上がったからにほかならない。
そこで、当会は、再提出された入管法改正案に対しても、以下の理由等により反対の意見を表明するものである。
- 送還停止効の例外の導入は難民の地位に関する条約に反するおそれがあること
政府は、入管法が規定する、難民認定申請中の者の送還を停止する効力に関し、3回目以降の申請を例外とし、3回目以降の難民申請でも難民等と認定すべき「相当の理由がある資料」を提出した場合には、いわば例外の例外として送還停止の効力が維持される、という制度を設けようとしている。
しかし、いかなる場合に例外の例外に当たるかの判断基準が明らかでない。
そもそも、日本は、諸外国に比べ難民認定率が極端に低いことが指摘されており、政府の難民認定手続が適切に実施されているとはいえない。かかる状況において、難民認定申請中の者に対する送還停止効に例外を設け強制送還を可能にすることは、日本が締結した難民の地位に関する条約が保障する、「生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない」という「ノン・ルフールマン原則」(難民の地位に関する条約第33条第1項)に反するおそれがある。。 - 退去強制拒否罪(仮称)は恣意的運用の危険があること
政府は、退去強制に必要な出国手続を取らない外国人に対して、かかる手続を取ることや退去することを義務付ける命令を発し、命令に応じない場合には刑事罰を加える制度を予定する。
しかし、同制度は、主任審査官が司法審査を経ることなく発付する退去強制令書に従わないことを理由として、刑罰を科すものであり、外国人の裁判を受ける権利(憲法第32条)を侵害しかねない(難民不認定処分に対する異議申立棄却決定が告知された直後の送還は、裁判を受ける権利を侵害等するものであり違法とした、令和3年9月22日東京高等裁判所判決参照)。退去強制令書の発付を受けた者の中には、帰国すると生命・身体に危険が及ぶ者や、日本に扶養を要する家族がいる者など、そもそも帰国できない事情を抱える者が存在する。政府が、対象者を限定する運用を行う予定であるとしても、同罪の構成要件に運用上の考慮事項を全て盛り込むことは不可能であり、結局当局の恣意的運用の余地を残し、保護されるべき者の権利を侵害する危険がある。 - 国際人権(自由権)規約委員会が示す入管法改正の方向性に反すること
国連総会で採択された自由権規約の実施を監督する国際人権(自由権)規約委員会が、2022年11月30日付けで日本に対して発表した総括所見では、①国際基準に沿った包括的な難民保護制度の創設、②国際基準に沿った収容中の医療アクセスの改善、③仮放免中の者に対する生活支援及び収入を目的とした活動の承認、④独立した司法による難民不認定処分の異議申立審査制度の創設、⑤現在行われている収容に代替する措置や収容期間の上限の導入、⑥現在の原則全件収容主義の転換、及び、必要最小限度の期間に限った、収容の謙抑的な運用が求められている(上記総括所見第33項)。入管法の改正に当たっては、以上の総括所見をふまえた、難民が間違いなく「難民」として認定される制度への改善、外国人等の生活保障及び現在の収容制度の改善が先決である。入管法が制度として問題を抱えていることは、2019年、長崎県大村市に所在する大村入国管理センターの被収容者がハンガーストライキにより餓死したこと、その後も東京出入国管理局や名古屋出入国管理局において、被収容者の死亡事件が相次いだことからも明らかである。 - よって、当会は、入管法改正案に反対するものである。
2023年(令和5年)4月20日
長崎県弁護士会
会長 山 下 肇